今日も暑かったですね〜
皆さん、お元気に一週間をお過ごしになりましたか?
もう午前1時を過ぎてしまいましたので、日曜日になってしまいましたので、昨日という事になってしまいますが、サッカー観戦のために予定よりもブログ出す時間が遅くなってしまいました。
今日は明治神宮の菖蒲園に行きました。
今が見ごろだという事でしたが、いささか日中は暑いので、少し落ち着いた時間帯に行きました。
そして、丁度閉館までゆっくりしてから、家に戻り、サッカー観戦をしました。
日本勢は、優勝候補のオランダと試合をして、良く最後まで頑張りましたが、点数には結びつかず残念でした。
しかし結果はともかく、スクラム組んで自分たちのやりたいように頑張れたら、それはそれで恥ずかしい試合ではないわけですから、次の試合に繋げる事が出来ると思います。
さて、サマ―フェスティバルにご出演される一部の若手アーティストを紹介していますが、今日で10人目をお迎えします。
今日は、ホルンの上原健史郎さんにお願いしました。
●こんにちは!前回は、同じ管楽器でもチューバ奏者でしたが、今日はホルン奏者です。上原さんは、いつからホルンをはじめられたのですか?
上原健史郎:僕は15歳からです。中学の吹奏楽部がきっかけで、初めはチューバとユーファニアムを担当していました。
●管楽器の方は、色々な楽器を弾かれるようですね。 そして、ホルンの魅力を教えて下さいますか?そして、何故ホルンに転向したのかなども・・・
上原健史郎:ホルンはとても優美な形状です(笑)
●そうそう。誰でもちょっと持って吹いてみたくなりますよね。
上原健史郎:もちろん音色も素晴らしいですが、ホルンに転向したきっかけは形状にまず魅力を感じたからだったと思います。
●そうなんですね。 形に惚れ込んでしまったというわけですか〜何となく分かるような気がします。
子供たちは、フランスのコンセルヴァトワールでは、ヴァイオリンとチェロのレッスンを毎週交互に受けて、半年後にどちらが好きか、と本人に聞いて好きな方を選択するという選び方をします。
娘も息子もまず大きくて格好いい、という事で2人共チェロを選びました。
それから、段々チェロの音色に惹きつけられていったのですが、最初は、結構単純に「格好いいから!」で選んでしまうところがありますよね。
娘もチェロを好きだったのですが、毎週レッスンのたびに運ぶの重いでしょう〜ピアノは持ち運びしないで、コンセルヴァトワールのレッスン室のピアノを借りれるので、最終的にはピアノを選んだみたいなところがありますよね。 (笑)
ところで、上原君は今まだ大学生でいらっしゃるから、色々将来の夢も沢山持っていらっしゃると思います。
今後の進路と言ってもこれからだと思いますが、どのような形で音楽と関わって生きていきたいと思われますか?
上原健史郎:僕は、音大を卒業したら、楽器店や音楽教室のホルン講師としてホルンを教える仕事に携わりながら、ずっとプレイヤーとしても活動していきたいです。
●そうですか。両立することは大変ですが、生徒たちから教えられる事も沢山あるんですよね。
私も教職やプライベートレッスンをかれこれ35年間に渡りしてきた事になりますが、生徒たちからたくさんの事を学ばせてもらいました。
どの子にもいいところがあって、でも色々な表現の仕方をしていておもしろいです。
こちらは出来るのが当然だと思っているような事がある子に取ってはとっても難しい、という事もあります。
そういう時は、自分で弾くという難しさとは別に、何故これを理解できないのか、をじっくり考えていくことで、教育者として一つ学ぶ事が出来るんですよね。
お若いですから、どんどん経験を積まれて、プレイヤーとしても教育者としても素晴らしい魅力的な方になって下さい!
上原さんは、誠実で真面目でお若いのにしっかりしている、といつも思っています。
頑張って進んで欲しいですね。では、好きな作曲家にいきましょうか。
上原健史郎:ラヴェルが好きです。
教育実習でラヴェルの曲を取り扱ったのですが、すごく好きになってしまいました。
●そうですよね。私は、学生時代からフランス音楽をするにもドビュッシーの方が多く弾く機会がありました。
ラヴェルは、ソナチネぐらいしか知らなかったように記憶しているんですが、フランスに渡って、娘がラヴェルの孫弟子に習った事もあり、あらゆる曲を知るようになると、何かとても不思議な魅力を感じます。
音型が、ある時はジャズ風であったり、ある時にはオリエンタル調であったり、何かしら耳にいつまでも残る不思議な響きがあるんですが、それがとても心地いいのです。
サマ―フェスティバルで演奏なさって下さいます、”R.シュトラウスのホルン協奏曲第1番”の魅力を教えて下さい。
上原健史郎:はい。それは、作曲家は、ホルンの事を知り尽くしているので、上手く言えないですが、ホルンらしさが沢山詰まっていて、なお且つとても聴きやすい曲だと思います。
●ホルンを知り尽くして作曲してくれた曲なのですね。
これは奏者にとって一番有難い事だと思います。
よく楽器の事を知らないで作曲された曲は、本当に弾きづらいですよね。
弦楽器でも知り尽くしていない作曲家が作られる曲は、演奏家を泣かせます。
よくぞ、こんなにややこしい常識では考えられないような指番号にしてくれたわね!と怒鳴りたくなりますね。
とにかく音程をはめるまでが、ただ事じゃなかったりしますから・・・
では、”R.シュトラウスのホルン協奏曲第1番”をサマ―フェスティバルで聴かせて頂けるのを今から楽しみにしています。
上原健史郎:ありがとうございます。
そして、この曲はオーディションやコンクールなどでもよく取り上げられるので、ホルン吹きにとっては避けて通れない曲なんです。
●ホルン奏者にとって、とても大事な曲であって、且つとても聴きやすい曲というのですから、これは最高!です。
”R.シュトラウスのホルン協奏曲第1番”の素晴さと魅力を是非多くの方たちに聴いて頂きたいですね。
皆さんもホルンの演奏を知らなくても聴きたくなってきたでしょう?
是非皆さん、杉並公会堂に足を運んでみて下さい。幸せな時間がまっていますよ〜

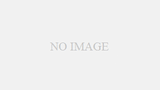
コメント