皆さん、梅雨に入り今日も湿度が高くムシムシしていましたね。
カメルーン戦は、いや~ドキドキしたけれど、本当に「がんばれ!日本!」で応援していました。
何とかオランダ戦もこの勢いで頑張って欲しいものです。
今日は、結婚記念日でした!
家族に祝福されて、今はパーティ後なので、アルコールが入っていい気分になっています。
今年で?年になりますが、結婚した時は、まさかそれから数年後にフランスに渡り、ずっとフランスで25年間も生活するとは夢にも思いませんでした。
もちろん海外生活は大変な事もあるし、色々な事があったけれど、自分の思い通りに生きてきて、振り返ってみると今までは幸せだったと思います。
これからも自分らしく、そしていつも他人のために頑張りたいし、優しい気持ちで生きていけたら何も言う事ないですね~
あとはみんなが健康でありたい、と思うだけです。
さて、今日のインタヴューは、7月27日第一部のトップバッターである、チューバの本橋隼人さんにご登場して頂きます。
●こんにちは!
チューバという楽器はご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。
管楽器の中でも特に大きい楽器です。コンサートチラシの本橋さんのお写真にチューバも一緒に載っていますので、ご覧下さい!
まず、チューバを吹くようになられたきっかけはいつ頃ですか?
本橋隼人:小学校に金管クラブがありまして、5年生の時に初めてチューバを吹きました。
●小学5年生というと金管楽器としては、かなり早い時期から開始なさられたのですね。
本橋隼人:はい。当時は、今みたいに男子が少ない状況ではなかった気がします。同じ学年に5人いて、最初全員トランペットのマウスピース・・・しかも本物ではなくプラスチックを吹きまして・・・で、音が鳴らなかったら他の楽器へいくっていう感じでパートが決まりました。
●面白い決め方をしたんですね。
本橋隼人:そうなんです。あとチューバは大きいですから、肺活量がいると思われますよね。それで、日本だと体がガッチリした人、つまり太っている人ですね。そういう人は肺活量があると思われるから、「君はチューバに相応しい!」っていう図式がありまして・・・(笑)
●確かに管楽器=肺活量がある、って昔から決めつけているところがありましたよね。でも、本橋さんの場合は、その体だからチューバ吹きがパスしたって事ですから、先生に感謝しないといけないですね。当時の先生の選択がなければ、今の本橋さんはありえなかったという事ですから・・・
本橋隼人:そういう事になりますね。実際は、まぁ大きな楽器ですから肺活量があった方がベターだと思うんですが、肺活量は横にいくら広がってても関係ないですからね(笑)
●そうそう、確かにそれは言えていますね。私なんか小学校時代から一貫してチビでしたが、ずっと歌をしていたからなのか、それとも肺活量があったから自然と歌いやすくてはじめたのかは分かりませんが、クラスの女子で一番肺活量がありました。そしたら、父も肺活量がすごくあったそうですからこれも遺伝ですね。
でも、肺活量=金管楽器 みたいな図式は素人の域の事で、何でも楽器はもっともっと色々なものの関わり合いがあって深いですからね、そんなに単純ではありませんよね。手が大きいからピアノをしておけばよかった、とか皆さん結構勝手な思い込みで意見するけれど、実際には、音楽のイマジネーションがどれくらいあるか、そこのところが才能の中で最も大事な事ですから・・・
でも今はこうやってチューバと巡り合って生き生きと元気に頑張っているわけですから、かなり早い時期にチューバの魅力に取りつかれたのではないですか?
本橋隼人:はい。小学校でやりはじめて割とすぐにチューバが好きになったように思います。花形のトランペットやサックスより低音の音や存在位置に魅力を感じました。多分、縁の下の力持ち的なとこも自分には合っている気がします。
●フムフム、そうなんですよ。実はコーラスでもバスの音が大事、アンサンブルでも通奏低音が実は一番大事な土台なんですよね。
家だってモダンで素敵なシャンデリアで飾っていても、土台が出来ていなかったら、素敵な家が倒れてしまいますからね~(笑)
本橋隼人:地味と言われますが、実はチューバは影の支配者なんです(笑)
●パチパチ(拍手)
本橋隼人:例えば、オーケストラや金管五重奏のような室内楽には基本的にチューバは一本ですが、面白いことにチューバ吹きが変われば同じバンドでも音色がガラッと変わります。上手なバンドには、大抵上手なチューバ吹きがいたりします(笑)
●本橋さんのおっしゃる事、よく分かりますし、実際にこれは確かな事だと思います。とにかく土台がしっかりしていない建物はダメなんですよ。
チューバ吹きですべては決まると言って過言ではないと私も思います。
本橋隼人:そうそう。だから、地味どころか実は主導権を握っているんです、チューバは!(笑)
●いや~本橋さんは、チューバの重要性を分かって、チューバを愛して、吹き続けている!って事がよく伝わってきます。頼もしいですね~
サマ―フェスティバルで拝聴するのを楽しみにしています。
ところで、サマ―フェスティバルでは、3曲吹いて下さいますが、選曲について何かおっしゃりたい事があれば・・・
本橋隼人:今回3曲ともチューバのオリジナルソロ曲を選曲しました。しかもジャンルはバラバラなんです。(笑)これは、お客様に色々なチューバの面を見て、聞いて頂きたいと思ったらからです。
●お客様のために考えて下さったというわけですね。
本橋さんは、パーシケッティ、ニュートン、ドミトルの3曲を聴かせて下さいます。吹奏楽の専門の作曲家は中々馴染みがないと思いますが、素晴らしい曲ですので、是非聴きにいらして下さい。
本橋隼人:しかし、そう言っても今回で生演奏を聴くのが生まれて初めて!という人が多いかと思います。世界的に考えればインターネットの発達で、もうチューバが新しいものだという考えはありませんが、日本ではどうでしょう?「あぁ~あのでかくて重い楽器ね」とか知らない人も多いです。ソロ曲を生で聴く機会も少ないですし・・・
自分も色々な場所で演奏させて頂いていますが、初めて聴かれるお客さんには、「チューバって素敵です!」とコメントをよく下さいます。今回ちょっと難しい現代曲も選択しましたが、三曲通して少しでもチューバの音色と音楽を楽しんで頂けばと思います。
●本橋さんは、中々色々詳しく意見して下さるので楽しいですね~
このブログを読んで下さっている皆さんも絶対に「チューバの音色を聴いてみた~い!」って思ってくれたような気がしてとても嬉しいです。
こうやって自分の楽器をアピールしてくれることは、本当にいい事だと思います。
ちょっといつもよりも長くなってしまいましたが、好きな作曲家はいらっしゃいますか?
本橋隼人:好きな作曲家はいっぱいいますが、敢えて言うなら、バッハ、ベートーヴェン、モーツァルト!
●クラシックの主要人物ですね。
本橋隼人:なぜなら・・・その時代にまだチューバが生まれてないから(笑)色々経て、チューバとして活躍するのは、1835年からなんです。
●そうなんですね。1835年なんですね。今日は色々勉強させてもらっています。
本橋隼人:昔ドイツのオーケストラの入団試験にコントラバスの実技も課題に入っていました。チューバは、出番が少ないのでそれ以外は、チューバ吹きもコントラバス奏者としてオーケストラに出演していたのです(笑)
●それは、私も聞いた事がありますが、大変でしたよね。打楽器の人が色々な楽器を扱うのは、あくまでも打楽器ですけれど、金管楽器とコントラバスの弦楽器では、耳だけは”通奏低音を追う”って言う事で共通点はあるにしても、口で吹くのと弦を弓で弾くのとはあまりにも奏法が違いすぎますよね~
本橋隼人:正直弾けるものなのでしょうか?第九とか相当難しいし・・・そしてギャラは(笑)現在はそんなことありませんが。あっ!あといらっしゃいました。ワーグナーです。チューバいっぱい活躍しますよ。あの管弦楽の使い方には無限の宇宙を感じます。
●ワーグナーの音は、厚みがあって確かにチューバに頼らなければ、あそこまで規模が大きくはならないですよね。大学時代、オケでヴァイオリンをしていた時に”マイスタージンガー”を演奏した時には、何故こんなにスケールの大きい音楽が出来たのだろう!って思いましたが、これは、「チューバ」が犯人だったという事ですね。”タンホイザー”なども凄い迫力ですよね。
最後に今後のご予定は?
本橋隼人:今後は好きなチューバをもっともっと勉強して・・・先程も話しましたが、日本ではチューバの生演奏が本当に少ないので様々なスタイルでの演奏活動もいっぱい増やしたいでっす。そして、少しでもチューバの魅力を幅広い世代の人にお伝え出来ればと思います。現在ソロや金管五重奏をはじめ、様々な構成の団体でチューバの可能性を日々追求しています。
●今日は貴重なお話を色々有難うございました。
聞いているだけでも十分チューバの魅力が伝わってきました。
多くの方たちに是非チューバの音色を聴いて頂きたいですね。
本橋隼人:サマ―フェスティバルで皆さまにお会いできるのを楽しみにしています。
●今日は楽しいブログになりそうですよ~

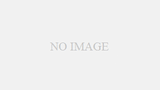
コメント