今日はショパンの命日です。
ポーランドのワルシャワの聖十字架教会でモーツァルト「レクイエム」を聴いたのを思い出します。
明日からいよいよショパンコンクールのファイナルですね。
先日オランジェリー美術館に行った報告のブログを書きましたが、あのモネの大連作の「睡蓮」を観たら、どうしてもモネのアトリエに行きたくなり、今日、ノルマンディー地方のジヴェル二ーまで出かけました。
セーヌ川沿いのパリから西方70kmの場所にあります。
まだ貧困時代の43歳から息を引き取った89歳まで住んだ家です。
秋の花が庭いっぱいに咲き乱れていました。
今はアトリエがモネのお土産屋さんになっていますが、これだけ大きなアトリエだったから思いっきり「睡蓮」を描けたのでしょうね。
モネの作品は、オランジェリー美術館にあるので、ここにはコピーしかありませんが、日本の浮世絵が大好きだったと言う事ですが、これほど沢山の浮世絵コレクションが、ジヴェル二ーで観られるとは思いませんでした。
モネは、1840年にパリの雑貨商の家に生まれたのですが、モネが5歳の時には父の商売がうまく行かなくなって、輸入雑貨商を営む義兄のいるル・アーブルに移転しました。
モネは、ル・アーブルの北の海の自然が大好きで1日中遊んで、学校にも行かず絵を描いていたそうですが、こういう子供時代を送っていなかったなら、これだけの作品は残せなかったでしょうし、自然を追い求めなかったのではないでしょうか。
モネは、自然を心から美しいと思ったから、その情熱で意欲的に自分の直感と霊感で自分の思いを自由自在に筆で自分の世界を描きました。
それだからこそ、後世の人たちが彼の作品に魅せられるのだと思います。
オーストリア人のゲーテルは、アインシュタインと話し合い、「数学の創造には情熱・直感・霊感が関与し、“芸術”と同じだ。」と語っていますが、数学の創造も芸術の創造もまさに同じだと思います。
練習を積んで身につける、というものは”真の芸術”ではないと思います。
とにかく幼時期から創造力を働かせる事ができる環境が必要な気がします。
私はすぐ教育に焦点をあててしまいますが、音楽を学ぶ姿勢も同じだと思います。
情熱があって磨かなければ光らないでしょうし、長続きもしないでしょう。
「睡蓮」は、フランス語で「水の精」という意味を持ちますが、モネが生涯追い続けた「光と水」をジヴェル二ーの家で発揮できたのですね。
この家こそ、光によって変化する自然の美を我がものにした最高の場所だったと思います。
今日も秋晴れでノルマンディーの風景は黄葉で眩しい光を放っていました。
こんな素晴らしい自然があるから、芸術が存在するのですね。

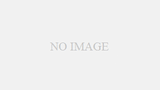
コメント