今日から夏時間です!
日本との時差は7時間になります。
フランスでも一時期は夏時間をやめよう、という動きもありましたが、結局ずっと続いています。
家中の時計を直さないといけないので、面倒な事もあるんです。
渡仏して間もない頃は、コンサートの時間をまちがえて、一時間外で待った事もあったし、逆にバスティーユのオペラ座で「カルメン」を観るのに、うっかり遅刻した事もありましたが、さすがにこう長くなるとそういうドジもしなくなりました。
急に日照時間が長くなってきましたから、旅行客にとっては、一日たっぷり散策できるようになりましたからいいですね。
パリって不思議なのは、ちょっと仕事でセーヌを横切るだけでいい気持になれますし、トロカデロの駅に出ると、エッフェル塔をシャイヨー宮から眺めてみたくなります。
用事もないのに、シャンゼリゼ通りに出てみたり・・・
ところで、昨日はフランスのよくない例をあげましたが、文化をはじめ、素晴らしいところも見てあげないとかわいそうです。
歴史的建造物は何と言っても素晴らしいと思います。今日はちょっとフランスの音楽教育について書かせて頂きます。
音楽教育については、私としては両国を混ぜ合わせたものがいいのではないかと思っています。
フランスでいいところ・・・
それは、教育の”教”でなく”育”を行う教授が多いように思われます。
育てる為の手助けをするけれども、教え込もうとはしない、というところです。
前に、「天才を待つ国」と言いましたが、真にそれが強いと思います。
将来自分を見失わないで羽ばたけるように導いて行くような教育は、とても優れていると思います。
これは但し結果が出るのに時間が掛かりますから、今の時代のように「コンクール」が年少者程受賞しやすい時代には向きません。
私は、冷静に”教育”を考えてみますと、慌てて上手にしていかなければ間に合わないような教育方針はどうも賛成出来ません。
しかし、フランスの音楽教育は遅すぎると思います。
2007年に他界なさられた、チェリストのロストロポーヴィッチは、パリの市庁舎での祭典でロストロ・ポーヴィッチコンクール会場を何故パリにしたか、をお話なさいましたが、その言葉がとても印象的でした。
彼はロシア人です。
ロシア人は、情熱的で熱いものを持ち合わせている国民ですから、とても芸術に向いていると思っています。
その彼が、「全世界でフランス人ほど音楽に向いている国民はいないと思います。フランス人が奏でる音楽は、優美で繊細そして感性があります。ですから、”パリ”が私のコンクール会場としては最高の場所だと思います。」と演説なさられました。
それだからと言って、フランス人がコンクールに受かるというのかというとそうではありません。
やはり賞を取るのは、ロシア人や他国籍の人たちなのです。
でも、第一次予選から聴いていますと、確かに”味”の面では、素晴らしい人がたくさんいると思います。
教授は教え込まないで、生徒は、全く自然体で自由に音楽を奏でますから完璧ではなく、コンクールのような減点法にはどうしても勝てません。
私もフランス人の奏法と歌い回しをこよなく愛していますし、ロストロポーヴィッチのおっしゃりたい事がよく理解できます。
パリの市庁舎での祭典の時にロストロポーヴィッチがフランス人を褒め称えましたら、フランス人はおっちょこちょいですから、「ワオー!」と大歓声が起きました。
やはりどこの国でも自国を褒められる事は嬉しいことなんですね。
フランス人の演奏は、紛れもなくその人の演奏であり、アーティスト本人からの味が出てきますから、とても豊かな音楽性であると思うのです。
自分のものは自分のものですから、誰からも取られる事はありませんが、幼時期から無理に先生のコピーすることに精を出しすぎますと、あとで問題になることもあると思います。
賞を取る事だけを目標として、目先の事だけに振り回されてしまいますと、どんどん自分の良さを失ってしまうこともあるように思えます。
フランス子供コンクールでも1人1人自分の解釈で弾きますから、課題曲でも驚くほど違います。
それでいいんだと思います。
でも、その音楽の中にその子の魂がちゃんと乗り移っていますから、その子がこのように弾きたいんだ、という自己主張があるから、聞いていてまさに”その子の音楽”が伝わってくるのです。
子供のコンセルヴァトワールのオーディションをもし日本の音楽教師たちが聞いたなら、「これがコンセルヴァトワールの生徒さんの演奏なんですか?」と首を傾げると思います。
正直言って、まだまだ未完成なところが多々あり、日本のきちっと弾いている子を見慣れている先生でしたら、「これがフランスの音楽教育なのですか?レベルが低いんですね〜」と驚かれるでしょう。
しかし、この子はオレンジ色に表現していて、あの子はブルーで表現していて・・・とはっきり自分の音楽の色が出ていて、本人は満足しきって自分の演奏を披露していますので、本当に心から楽しめる演奏会をしてくれるのです。
まだまだ下手なのに潤いがあって、魅力的・・・というのを想像できますか?
ミスタッチだらけなのに、音が光っていて何を表現したいかが伝わってくるから、楽しいんです。
1人1人の解釈が違うので、この先生のお弟子さんという事が分かりづらいと思います。
”教育”とは本当に難しいですね。
先生たちは、わざと嫌がらせしようとして生徒に教えているのではなく、みな自分を信じて、生徒の向上を願って教育していらっしゃるのです。
しかし”教”に傾き過ぎている傾向にあるように思えてなりません。
人間は商品ではなく、1人の生きている人間ですから、パソコンの性能をどんどんよくするのとは違い、その子の生まれながらに持った感性をそのままにしてあげて、ゆっくり正しい道に導いてあげたいと思っています。
どんどん教え込みをした方が、親御さんにもわが子の進度が速いので喜ばれますし、結果がすぐ出ますから本人も一時期は満足してしまうのですが・・・
しかし日本からの留学生がパリにきて、「フランス人より弾けているのに何かが違う。」と感じてからノイローゼになってしまったり、「日本の先生の方がずっと丁寧に教えてくれたし、フランスの先生ってすごい大雑把だから・・・」と不満を持ったり、「もう十分弾けるんだから君はまず遊ぶことが必要だ!」なんて急に言われても困惑してしまう学生さんがいらっしゃいます。 「遊ぶ」という発想についても先生は美術館や観劇などを思っておっしゃっているのですが、日本で出来なかった「テレビゲーム」を購入して遊んでいる留学生もいました。
留学生の中には、「フランスの先生は、細かく教えないから翌週まで何をしていったらいいのかわからない。」という人が多いです。
言葉のすべてを理解できないですから難しい、という事ももちろんあるでしょうが、先生から何か与えてくれるものを待ってもダメです。
自分から質問するなりしなければ、あまり細かい事をおっしゃらない先生もいらっしゃいます。
でも、曲のイメージなどが違っている、と思われると、その曲の描写とかとても楽しく語って下さいます。
しかし、これは言葉の壁があるとそう簡単には理解できませんね。道を尋ねたり、お買いものの会話とは違いますから、難しいとは思います。
優等生で指回りがよくても、将来的には、それよりも、その子の生い立ちから出る感性と思考力、想像力、空想力、思想・・・それと勘などが実は一生を通じて演奏家としてはとても重要な要素だと確信しています。
”ゆっくり教育”ですとコンクールなどはまず受からないんです。
しかし、30代、40代で世界的には無名のアーティストが本当に美しい演奏を聴かせてくれることがあります。
ずっと”音楽の本質”を追い求めて、コツコツ勉強に励んでいる姿が見えてきます。
これはあっぱれな達者なアーティストにはない、頼りないナイーブなシルクのような音色なのです。
亡父は”すみれ”をこよなく愛していました。60年位”すみれ”と付き合っていたんではないかと思います。
「三色すみれももちろんかわいいけれど、パパは、この淡い頼りなくて優しい”すみれ”が大好きなんだよ。」と言っていました。
その時はあまり深く考えませんでしたけれど、何となく綺麗さにも色々あるんだな〜と、その言葉を思い出す事があります。
皆さんも自分の好きな音を見つけてみて下さいね。
有名アーティストでも無名アーティストでもいいんです。
自分にぴったりの、今の自分が求めているアーティストが必ずいると思いますから・・・
”技術”は指ではなく耳しかないんですから〜

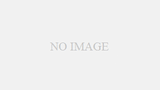
コメント