このところ、パリは晴天です。日中の気温が13度あります。
娘夫婦たちは4日に無事パリに到着しました。
7ヶ月の孫は、機内では興奮して寝なかったそうですが、それでも元気に家に着いてくれたのでホッとしました。
離陸と着陸の折に気圧の差で耳が痛くなる事がありますが、ちゃんとその時はミルクを飲ませていたので問題なかったようです。
夜は一緒に家でフランス料理を頂いて、翌朝には、娘夫婦だけでノルマンディーのモン・サンミッシェルに出かけました。
娘婿は一週間の休暇を取ってきたので、その時期は小旅行を計画しているようです。
昨日からは3日間、子供たちが15年間育ったアルザス地方のコルマールとストラスブルグに行っています。 3人で出かけてくれたので、今はちょっと一息ついています。
モン・サンミッシェルには一泊旅行でしたが、それでも時差がある中で、孫をすぐ引き取って大丈夫かしら?と少々不安でしたが何とか・・・
ただ、案の定夜中にはしゃぎだしてそれにつき合っているのがちょっと大変でした。
離乳食もはじまっていますが、試しにフランス製のビン詰を買ってきました。
ノルウェー産のサーモンなど日本では食べられないベビーの食材が色々あるので試してみましたが、どれも美味しかったようで、ペロッと食べました。
デザートもベビー用のフルーツやヨーグルトが出回っていますが、どれも手足バタバタして感激して食べてくれました。
とにかくあっという間に食べてしまいます。
スプーンの運び方がちょっと遅いと催促して大口を開けて待っています。
ところで、息子がチェロの練習をはじめると久しぶりに聴こえてくる音色に聴き入っていました。
遊具を使って遊んでいた手をピタッと止めて聴き入る姿は本当に可愛かったです。
自分の子供たちの音楽教育はほとんど歌を歌ってあげるだけで何かしてあげた記憶はあまりないのですが、ちょっと孫に実験的に色々な短い名曲を聴かせてみました。
膝の上に乗せながら一緒に音楽を聴いて体を動かすのですが、曲によって全然反応が違うのです。
聴かせた曲の中で一番のお気に入りは、ゴセックの「ガボット」でしたので何度も何度も聴かせました。
オクターブ跳躍のところで、体をジャンプしてあげるから余計なのかもしれませんが・・・
ピアノに向かうとママのまねのつもりなのでしょう。
デタラメ弾きでたたくのですが、この「ガボット」のメロディーを弾き始めると自分の演奏?をピタッと止めて最後まで聴き入るんです。
そして最後の音が終わると、また自分もガボットを弾いているつもりになって、デタラメ弾きをはじめるんですね〜
スメタナの「モルダウ」は、東欧の響きを持ちますので、始まると同時に何か怖い感じがするのでしょう。
神妙な顔をして聴いていましたが、不思議な音がちょっと気に食わないみたいです。
2回目には半べそかいて、音楽を止めるように声をあげていました。
サン=サーンス「白鳥」のような単純で綺麗なメロディーではこちらを向いて笑顔で答えていますし、ハチャトリアン「剣の舞」やリムスキー=コルサコフ「熊蜂の飛行」などのリズムのあるものは足をばたつかせて喜こんでいました。
英才教育というのではなく、子供の反応をみていくことはとても楽しいものです。
以前にピアニストの故グレン=グールドの対談の中で、産まれた時から毎日現代音楽しか聴かせなければ、耳はそのように育つ、と話していましたが、確かにベビーでも個性があり、それぞれのジャンルによっての反応は違うと思いますが、今からずっと無調の音楽ばかりを聴かせたなら、この子は、無調音楽が普通の音楽だと思うでしょうね。
それを試すつもりはありませんが・・・(笑)
遺伝と環境の両方が作用しているのですね。
生徒たちの反応も確かに親がどのジャンルの音楽を聴いているかによって格差がありますから、その子の好きなジャンルは親の影響が強いと思います。
娘が妊娠7ヶ月の時にレコーディングした、謝肉祭、アベッグ変奏曲、子供の情景は、産まれてからもよく聴かせるそうですが、とても反応を示すそうです。
赤ちゃんの時は、「ママこの音楽がもっと聴きたい!」とは口では言えないけれど、じっと反応の示し方を観察しているとすでに個性というのは出来ているものなのですね。
孫と楽しい時間を過ごすことが出来てよかったです。
これから毎日子育ての手伝いの日々ですから、今日はちょっと休憩しています。

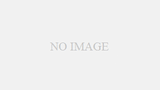
コメント