皆さま、お変わりございませんか。
無事、レ・クロッシュの仙台公演を終え、東京に戻りました。
行きに寄りました、福島県の猪苗代湖では、雪の中、困ってしまったことはありましたが、順調に予定通りに進みましたので、安堵しています。
仙台での一日目のリサイタルは、「びすた〜り」というレストランでのディナー付コンサートでしたが、とても趣がある木造建築で素敵なところでした。
お客様の層がとても落ち着きのあるお上品な方たちばかりだったせいか、静かなひと時の中での演奏となりました。
そこで驚きましたのは、2015年にお世話になりました、東松島での公演の主催者さんご夫妻+お父様と3人でお越し下さったことです。懐かしい再会となりました。
「レ・クロッシュの演奏はやはりすごいです!」とお声を掛けて下さり、心が熱くなりました。
ディナーの内容は充実していまして、素晴らしいメニューでした。
翌日から2日間は、レ・クロッシュのゲスト出演が4回という事で、私も譜捲りの関係で、着せ替え人形のように、着たり脱いだりしていましたが、仙台ピアノ工房のピアノ発表会は、今回も素敵な会でした。
2009年にも招聘演奏のゲスト出演をさせて頂いていますが、2014年には、レ・クロッシュがリサイタルをさせて頂きましたし、不思議な程、東北とのご縁が続き嬉しく思うと共に、このご縁に感謝しております。
東北のご縁の最初は、2004年に千葉のヤマハミュージック臼井店のコンサート依頼がございました折、臼井店長さんがヤマハミュージック郡山店の担当の方と懇意にされていらっしゃるということで、2006年に郡山店サロンホールで演奏させて頂きました。それがきっかけとなり、2007年には、郡山に近い須賀川文化センターにて、Eご夫妻の主催のもと、レ・クロッシュリサイタルを開催させて頂きました。
2008年には、再度ヤマハミュージック郡山サロンホール、2009年には、郡山店からのご紹介で、ヤマハミュージック仙台で演奏させて頂き、その秋、仙台ピアノ工房にて、ゲスト出演をさせて頂きました。
2010年には、福島県 いわきのアリオスホールでの公演を致しまして、2011年は、東日本大震災の為、4月に予定されていましたアリオスホールはキャンセルとなり、2013年に同ホールにてチャリティーコンサートを致しました。いわきの復旧復興工事が行われていた時期で、今でもその光景が焼き付いています。
そして、2014年6月には、須賀川のカナリヤ童謡の会 10周年記念企画公演では、中央公民館にて、レ・クロッシュはリサイタルに招聘下さいました。
企画して下さいましたのは、2007年の須賀川公演のEご夫妻です。
そして、同年9月には、仙台ピアノ工房 木造ドームホールにて、招聘演奏会をさせて頂きました。
2015年には、やはり仙台ピアノ工房のIご夫妻からのご紹介で、秋保温泉でのコンサートの翌日に、東松島での公演もございました。東日本大震災で被害が大きかった場所ですが、皆さまのとても明るくお元気な姿に嬉しくなりました。
この時の東松島の主催者である、Wご夫妻が、何とわざわざ11月24日の「びすた〜り」での公演にお越し下さり、ご挨拶をして下さった時には、懐かしくとても嬉しく思いました。
ご縁とは本当に不思議なものです。
最近、もしレ・クロッシュという存在がなかったなら、全く一生知るはずもない東北の方たちと、音楽を通じて、長いお付き合いが出来ているわけです。
これは、本当に凄い事であり、素晴らしい事だと思います。
ところで、仙台ピアノ工房でのピアノ発表会を、本番の準備はありましたが、なるべく多くの生徒さんの演奏を聴きました。
ちょっと、我が子たちが通っておりました、フランスのコルマールコンセルヴァトワールの発表会を思いだしてしまいました。
フランスの教育の素晴らしいところが、この仙台ピアノ工房さんでは、そのまま活かされていると思いました。
フランス人は感性があると言われています。
チェリストの故ロストロポ―ヴィチがコンクール場所をパリにした理由として、フランス人が全世界で一番感性があり、心豊かな演奏をする人が多いのでこの地が私のコンクール場所として相応しいと思い決めました、とおっしゃった事を思いだしました。
ロシア人はやらせが多く、本来の音楽の美しさはフランス人にはかなわないとおっしゃっていました。
確かに感性があるからこそ、小さな子供たちが弾いても先生のコピーではなく、完全に自分自身で作りあげた音楽を聴かせてくれるのだと思います。
指は回らなかったり、弾き直しは日本人に比べると確かに多いのですが、何時間弾いてくれても飽きないで、次の子の個性は?というような聴き方が出来てとても楽しいひと時なのです。
どうしても発表会となると、先生が教えなければいけないところに留まらず、そこからもっと発展して、一生懸命お化粧してあれこれ色をつけてしまったりすることが多いと思います。
その気持ちもよく分かるのですが、フランスに渡ってから音楽教育法を色々考えましたが、無理のない自然体で弾く事が一番であること、この子の演奏を是非また聴いてみたい、と思うような演奏に仕上げる事が今後のその子の発展のために大切な事だと思います。
子供はそれぞれに可能性があり、音楽は十人十色なのですから、子供が作ってきた音楽を大切にし、損なわないようにして、そこに不足している物を指摘して、どんどん伸ばせるような教育法が一番よいと確信致しました。
とにかく、何と言っても自分の耳で確かな音楽を見つける方法を身に付けてあげられれば、教育はそれに尽きると思います。
よい音楽を聴かせてあげてまずは音楽を好きにすること、そして、音楽は本来楽しいから続けていくものであるのですから、あとはマイペースでどんどん好きな方向に進んで行けばよい事だと思います。
もともとスポーツしか興味がなくて、音楽は嫌いだ!という子どもには、無理強いしてさせる必要もないわけですし…
自分で一生かけて好きなものを見つけられれば良い事なのです。
仙台のお子さまたちは、とても大人しい子が多いのですが、自分を見つめじっくり考える能力のある子が多いと思いました。
音楽は、素朴な中で育っていくような気がします。
音の多い賑やかな生活の中では、自分自身を見つめる事が難しいですから、そういう点では地方で学ぶ子どもの方が恵まれていると思います。
2007年のゲスト出演の折にもその件に触れてお話させて頂きましたが、今回もその子供たちの健気に頑張っている演奏を心から応援したくなりましたし、これこそ素晴らしい教育法だと信じています私に取りましては、とても嬉しかったです。
Iご夫妻とは長年の友人のような気持ちでお付き合いさせて頂いていますが、何か音楽の原点を見失わずに着実に生徒に寄り添って個々の性格を考慮しながら伸ばしてあげていらっしゃるから、親御さんたちもご安心なのでしょう。
Iご夫妻の性格の良さからくるものもありますし、講師の先生たちに恵まれている事もあると思いますが、益々頑張って欲しいと願っております。
では、私もまた原点に戻り、一番大切な子どもの教育について、考えてみたいと思います。
寒くなりましたので、くれぐれもご自愛下さい。

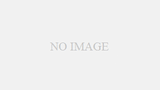
コメント