皆様、急に気温が低くなってまいりましたね。
お元気でいらっしゃいますか?
私は、名古屋と大阪で週末を過ごしました。
コンサートのためとはいえ、今の日本の自然を十分に満喫でき、幸せな日々でした。
地方に行くと、仲の良い友人に会える事も楽しみの一つです。
何よりも、コンサートによって、皆さんが満足して喜んで下さることが一番嬉しいです。
「紅葉」と「音楽」が共通している美しさ、紅葉に限らず、「自然」と「音楽」の接点について旅行中の景色を眺めながら感じました。
名古屋や大阪の紅葉も素晴らしかったですが、何といっても彦根城周辺は、紅葉の最盛期で見事した。
彦根城のお堀に移る紅葉の陰と紅葉とのバランスが抜群でした。
今年の彩りは素敵だと思いましたが、絵葉書を見ても分かるように、毎年、紅葉の色合いや様子、色の濃さ、そして木の成長により、違う顔で、訪れる人たちを楽しませてくれます。
これだけ風景が毎年違うので、写真家も同じ場所に何度も何度も足を運び写しにくるのですが、一度として同じ顔にならない、「自然」を最高に美しいと思います。
音楽は、生きている人間が奏でるわけですから、その日の精神状態、体調、演奏する場所の環境、お客様の反応・・・もっともっと色々な違う条件の中で、音色、響き、曲想、曲に対する思い入れなどにより、その日の演奏が出てくるわけです。
これが生演奏の醍醐味なのだと思いますが、きちっと綺麗に演奏をした人だった、というのと、味わい深い演奏を聴くことができた、とは大きく違います。
1990年の頃の話です。
フライブルグ音楽院のピアノ教授のヴァルター先生は、とても人間的で魅力的な方でした。
彼の祖母がリストと一緒に写真に写っているような、音楽ファミリーです。
教育法は独特で、ピアノを弾いて理解させるよりもほとんど体を使って歌って教育していきます。
ショパンのマズルカなどは、自分でレッスンの間中踊っている方でした。
とても素晴らしい教育方法だと思いましたし、生徒たちの演奏を聴いていてもとても生きている演奏を聴かせてくれて楽しかったです。
しかし、生徒たちが次々と止めていく実態を目の当たりにして、原因を追及してみました。
ある生徒は、「先生としては最高で自分の持っている才能を引き出してくれる。でもこれでは20代で受けなければならないコンクールには受からない、本当に今の時代に生きていて残念です。」と残念そうに話していました。
ヴァルター先生のお弟子さんは、ソナタの第二楽章は、とろけるように音楽の世界に導いてくれるのです。
私は、第二楽章を退屈させないで魅せられる演奏家は最高だと思っています。
何故美しいのか、というと、「規則的でない」事なのです。
メトロノームできっちりではなく、呼吸と同じようにその時々のその時の気持ちで気持ちよく奏でるから周囲を自然と音楽の世界に引きずり込んでいくのです。
これこそ、真の音楽だと思いました。
ヴァルター先生は、「ピアニストになってはいけない、アーティストにならないとダメだ!」とおっしゃるのが口癖でした。
生涯を通じては、アーティストであることが最も重要なのですが、20代の学生たちには、今成功させないといけない、という現実があるので、中々こういうご年配の素晴らしいアドヴァイスを受け入れる事が出来ないと言うか、分かっていても将来を考えると、きちっとした正確な音とリズムで鍛える奏法を学びたいと思うのです。
実際には、甘いとろける音は、練習によって強硬に訓練された手で弾くのではなく、心のつぶやきを音に託するだけなのです。
それを引き出すためのテクニック訓練を行う事が演奏するにあたっての正しい訓練だと思います。
そして、これは柔軟性のある時期にやらなければ、歳を重ねてから、その事に気付いてやろうとしても、本物にはなりません。
思春期にどう音楽を受け止めるか、という事が一生を通じて大切な事だと思います。
要するに思春期にどういう人生を送ったかが、大人になってそれが音色として出てくるのです。
「紅葉」を眺めながら、生演奏は一回として同じ演奏になることはありませんが、今の自分の生きざまが音色となって出てくるわけですし、紅葉のようにその一瞬の色ではなく、一年間に経験した自然の暑さや寒さの厳しさにより色合いが変わるのですから、演奏もそれと同じで、どんな一年間を過ごしたかによって、その演奏から出てくる音色や色彩感が変化していくのだろう、と思います。
結論に入りますが、結局演奏家というのは、本人のその年の生きざまがそのまま演奏の音として出てくるわけです。
素敵な「紅葉」の色合いが出るように、価値ある、有意義な日々を送る事が、大切なのでしょうね〜
私は、演奏家ではないですが、人生の色は自分で決めているのですから、今年の色合いを確認しながら、来年に向けて磨きたいと思っています。

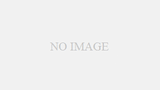
コメント