皆さま、お変わりございませんか。
藤の花も例年よりもかなり早いそうですが、春は芝桜や家周辺のつつじも見事で、散策が色鮮やかな道を歩き、とても楽しいです。
もうすぐゴールデンウィークが始まりますが、楽しいご予定を計画していらっしゃいますでしょうか?
ようやく4月のレ・クロッシュリサイタルを終え、5月4日のオペラシティ リサイタルホールでのリサイタルに向けて、調整をしております。
4月の公演は、4年振りのコンサート依頼というところが多く、本当に充実した時間でした。
どこの会場にもお客様がいっぱいで、すごい熱気を感じました。
主催者も、コロナ禍で死んだようになっていたコンサート活動が生き返ってきた、と大喜びされていました。
少しずつコンサートに行く習慣が戻ってきてほしいと思います。
未だに、舞台公演がキャストのコロナ感染者の影響で中止になったところも多いと聞きます。
先週、キャストのコロナ感染により、ダブルキャストを調整して、夜公演は中止でも昼公演は致します、との連絡に、地方からのキャストたちは飛行機で東京に向かいましたら、2時間前に、昼公演のキャストからも体調不良の人たちが出ましたので、昼公演も中止、となったそうです。
地方に住んでいらっしゃるキャストたちは、本当に大変だと思います。
ミュージカル出演が決まりました名古屋の高校生の孫のお友達は、午前中授業を受け、夕方からの東京でのミュージカル舞台練習時間に間に合うように学校を早退し、新幹線で東京に向かい、夜練習後にはまた新幹線の中で毎日宿題をしながら名古屋に戻り、それでも家でその続きをしていてからだと、就寝時間は、午前3時頃になってしまうのよ、とお母様が心配されていたそうです。
それを週に4回~5回続く生活だという事ですが、いくら若いと言っても体力的にも金銭的にも大変な事だと考えてしまいました。
ところで、すでにご連絡しておりますように、今年は、娘の指の不調により、ベートーヴェンのチェロソナタ第3番だけは、ピアニストの伊東晶子さんにお願いしていますが、何度か本番にも出演して頂きまして、よい感じのアンサンブルが出来てきましたので、とても嬉しく思います。
明日は、我が家での最後の合わせをして調整を致すそうです。
オペラシティリサイタルホールのホールにチェロとピアノのアンサンブルが響き渡って欲しいです。
ところで、「ぶらあぼ5月号」の6公演だけ「注目コンサート」として紹介されるページがございますが、そこに。5月4日の
「レ・クロッシュ リサイタル 〜ピアノ & チェロの夢の世界〜」が紹介されました。
eぶらあぼ 2023.5月号 (ebravo.jp)
注目公演の中に、深沢亮子先生は、何と「デビュー70周年記念コンサート」を5月になさらると知って、驚きました。
レ・クロッシュが20周年を迎えるだけで、色々大変だったな〜と私としては思っていますのに、70周年とは脱帽です。
渡仏前には、当時深沢先生に師事されていた先生にお世話になっていたこともあり、何度か深沢先生のリサイタルに足を延ばしましたが、近年は室内楽を好んで演奏されるそうで、今回も、シューベルトの5重奏「鱒」を演奏されます。
アンサンブルには、ソロにはない魅力がございますし、楽しんで演奏されることと思います。
私が学生時代の話ですが、深沢亮子先生のお父様に、音楽雑誌「音楽の友」の記者だったと思いますが、インタヴューをされた折に、「お嬢様の演奏を聴くのは、やはりドキドキするのではないですか?」と開演前の質問に対して、「演奏というのは生ものですから何が起きるか分からないものです。
しかし娘を信じていますから、最良の方法で何かあったとしてもそこを乗り切って演奏してくれると信じていますので全く心配はしておりません。」とお応えになったことを覚えております。
私自身も20年前の子供たちの演奏の聴き方と今とではかなり格差があるのを感じます。
まだ、子供たちがパリ音楽院時代の頃のコンサートの時には、演奏を聴きながら手に汗びっしょりで、「どうか、上手く弾けますように!」と祈りながら聴いていたと思います。
年月が経ち、「音楽鑑賞とは何か?」と考える時間が出来たこともありますが、「演奏者が自分の演奏を楽しんで弾いたなら、お客様も必ず幸せな気持ちになれるものだ。」と思った途端に、親として聴き方が随分変化したと思います。
パリの教授たちも口をそろえて、子供たちに、「素敵な演奏をして、お客さまの心が熱い思いで涙を出してくれるような演奏をしていらっしゃいね。」と日本に送り出してくださったことも、今考えますと最高の先生たちに巡り合えたと思っております。
確かに人間ですから、いつ何が起きるかは分かりません。またそれが生の演奏であり、ロボットには出来ない事です。そのホールの空気の中で、観客と共有して今の音楽の時間を楽しむ、という気持ちが増してきますと、ミスタッチ云々ではなく、深沢亮子先生の御父上と同じ心境だな、と感じる事がございます。
コンピューターの時代に入り、何でもできてしまいますが、生演奏というのは特別な状況ですから、機械のように精密でないからこそ、魅力があるのだと思います。
正確さだけを求めて音楽を聴くならば、別にCDでも構わないわけですが、音楽の呼吸を一緒に味わうことは、生演奏でしか味わえない事です。
昔、娘がドイツ フライブルグ音大付属の英才音楽教室に通っていた頃に、W大先生から、ピチッと粒ぞろいに演奏をするよりも、耳で聴いて心地よい音階を弾けばいいんだよ、と言われた時に、自分の頭で考える音楽教本にはないことで驚きましたが、フライブルグで、W先生が、シューマン「交響的練習曲」をリサイタルで弾かれた時に、W先生は、何をおっしゃりたかったのかが手に取るように理解出来ました。
音楽は「耳」で美しいと感じるものを見つけていけばよい、と言う結論に達しました。
その後パリに渡り、パリのアーティストもまさに自然なメロディーを重視していますし、どこにも器械的な音階など存在していませんでした。
こればかりはロボットにも出来ないだろうな〜と実感しました。
ということで、とにかく人間の耳というのは素晴らしいものであるという事です。
耳がよい音を見つけるから、感動があるのです。
W先生が、娘に、「人間は呼吸をしているけれど、必ずしも完全にピッタリ正確に呼吸しているわけではないでしょう。速かったり遅かったり、必ずしも一緒でないんだよ。演奏も人間の奏でる音楽は、機械的に正確に弾くというのではなく、耳で心地よい音の繋がりこそが、聴衆の心を魅了させることになるんだよ。」という教えは、最高の教えだと思います。
子供教育はある程度正確さを身につけなければなりませんが、大人の音色は音色の繊細さやダイナミックさ、とろけるような甘い音、激しい怒り狂ったような音色、作曲家がどのような心境で作曲したのかを紐解きながら、演奏を弾いたり聴くことこそ、楽しい時間だと思います。
では、皆さま、楽しいゴールデンウィークをお過ごしくださいませ。

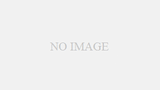
コメント